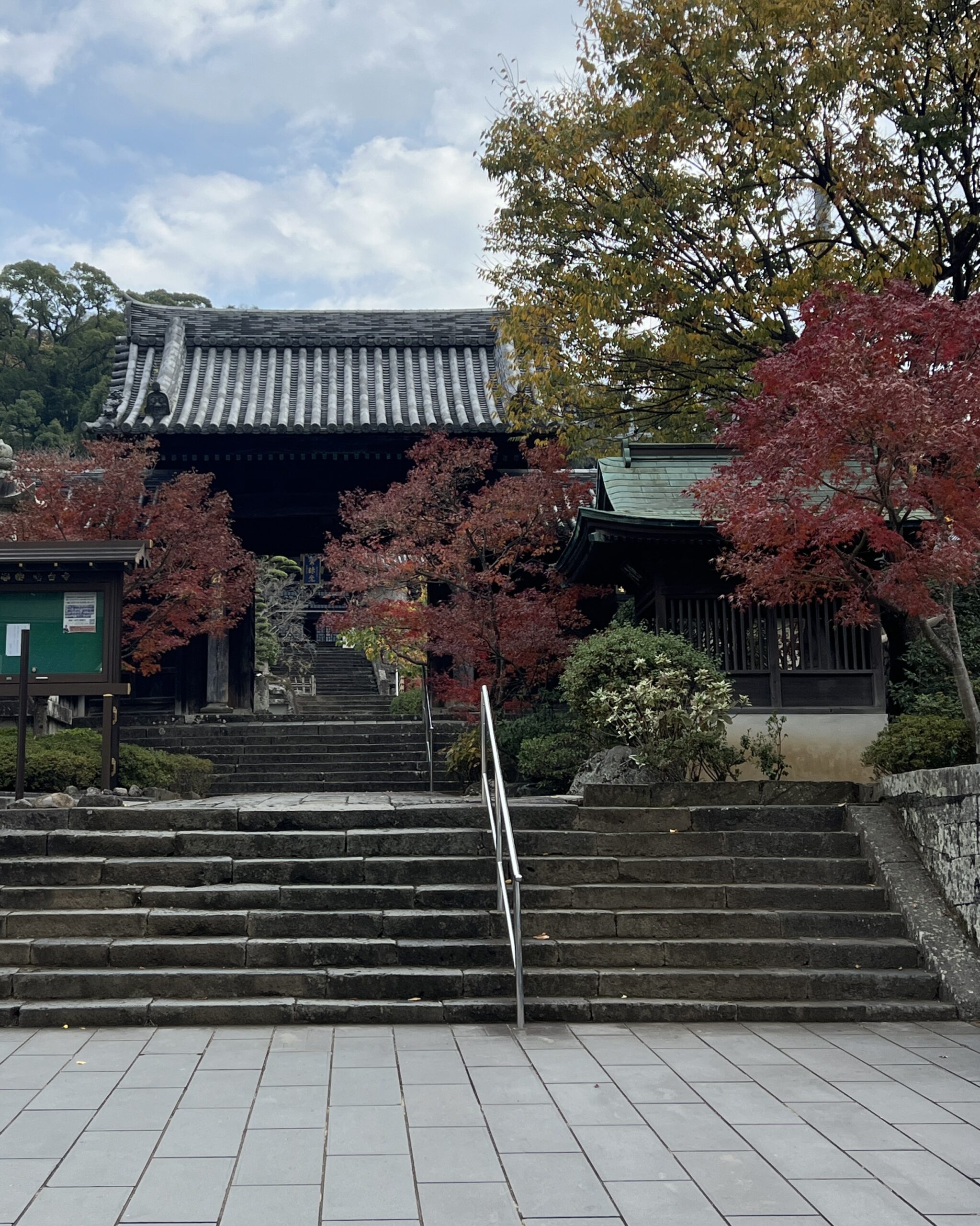AI開発と著作権法について。
目次
AI・ディープラーニングの全体像
- 人工知能
- 機械学習
- ディープラーニングの基本・応用
- ディープラーニングの研究
- AIプロジェクト
- AI社会実装に伴う法律・倫理
著作物とは
著作物であるための条件
- 表現したもの(表現物)であること
- 思想又は感情を表現したものであること
- 創作的に表現する(創作性を有する)ものであること
- 文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する表現であること
- 著作権の成立→著作物の創作の時に始まる
- 著作権の存続期間→著作者の死後70年を経過するまでの間
- 法人等名義の著作物の著作権の存続期間→著作物の公表後70年を経過するまでの間
著作権の種別、侵害に対する措置
著作権の種別
- 著作物人格権
- 著作財産権
侵害に対する措置
- 差止請求
- 損害賠償請求
- 名誉回復請求
- 不当利得返還請求
共同著作権・共同著作物
- 共同著作物→2人以上の者が共同して創作した著作物であって、各人の寄与を分離して個別的に利用できないもの→共同著作権
- 共同著作権→共有者全員の合意がなければ共有著作権を行使できず、その持ち分の譲渡等はできない
職務著作
- 企業の従業員がその職務に関連して著作物を創作する場合のこと
- 原則として、職務著作の著作者は、法人その他の使用者
- 職務著作の要件
①法人その他の使用者の発意に基づき作成されたもの
②法人等に従事する者が、職務上作成したもの
③法人等が自己の名義のもとで公表したもの
AI開発と著作権
| 生データ | 生データの性質と生成の経緯による |
|---|---|
| 学習用データセット | 「データベース」としての著作権が認められる |
| プログラム ソースコード | コーディングされたプログラムの”表現”として保護されることがある |
| 学習済みパラメータ | 原則として数値であり、著作権は発生しない |
- 学習済みパラメータ→営業上有用な価値を持つ大切な財産であるが、著作権は発生していない
→営業秘密としての管理、契約による所有権や使用権の明確化など保護できるよう慎重に進める必要あり - プログラム言語・アイデア・規約・解放→著作権法による保護は及ばない
- システム設計書・プログラム設計書・ユーザー向け説明書→著作権法による保護が及ぶケースがある
学習データ利用、著作権侵害
- データの収集・保存→「複製」→著作権者の同意なく無断でコピー(複製権の侵害)してはならない
- データの加工・処理→「翻案」→著作権者の同意なく無断で編集(翻案権の侵害)してはならない
- 「著作権法第30条の4第2号」→他人の著作物をAI開発のために広く用いることを可能にする例外規定
- 「情報解析」
- 営利目的であっても、著作者の許諾なく無断で著作物をAIの学習に利用可能
- 著作権者の著作物の利用市場と衝突する、将来における著作物の潜在的市場を阻害する
→AIの学習への著作物の使用が著作権侵害となる - 日本の著作権法が及び日本国内に所在しながらの利用に限定される
AI生成物と著作権
- AIの支援を受けて生成したものが著作物になる可能性あり
- アイデアだけもらう場合、生成内容の顕著な部分を編集して活用する場合
- 生成AIを単なる道具として使っており、人間の創作性が十分にあったかどうかが決め手となる
- 生成AIに著作物を学習させた場合、その学習済みモデルによる生成物が著作権侵害を起こしやすいことに注意が必要
- 生成AIを用いた生成物が他者の著作物に依拠し、かつ、類似している場合
→著作権法の違反になる - 私的利用であれば原則として問題にならない(営利目的の利用のみ該当)
- 今後→どのようなコンテンツを生成AIに学習させているかを開示することが求められる可能性あり
- AI生成物が他の著作者の権利を侵害した場合→刑罰の対象となりうる
- 「ハルシネーション(幻覚)」リスク
- 医療・経済・法律といった高リスクの専門分野→生成AIの利用が厳しく規制