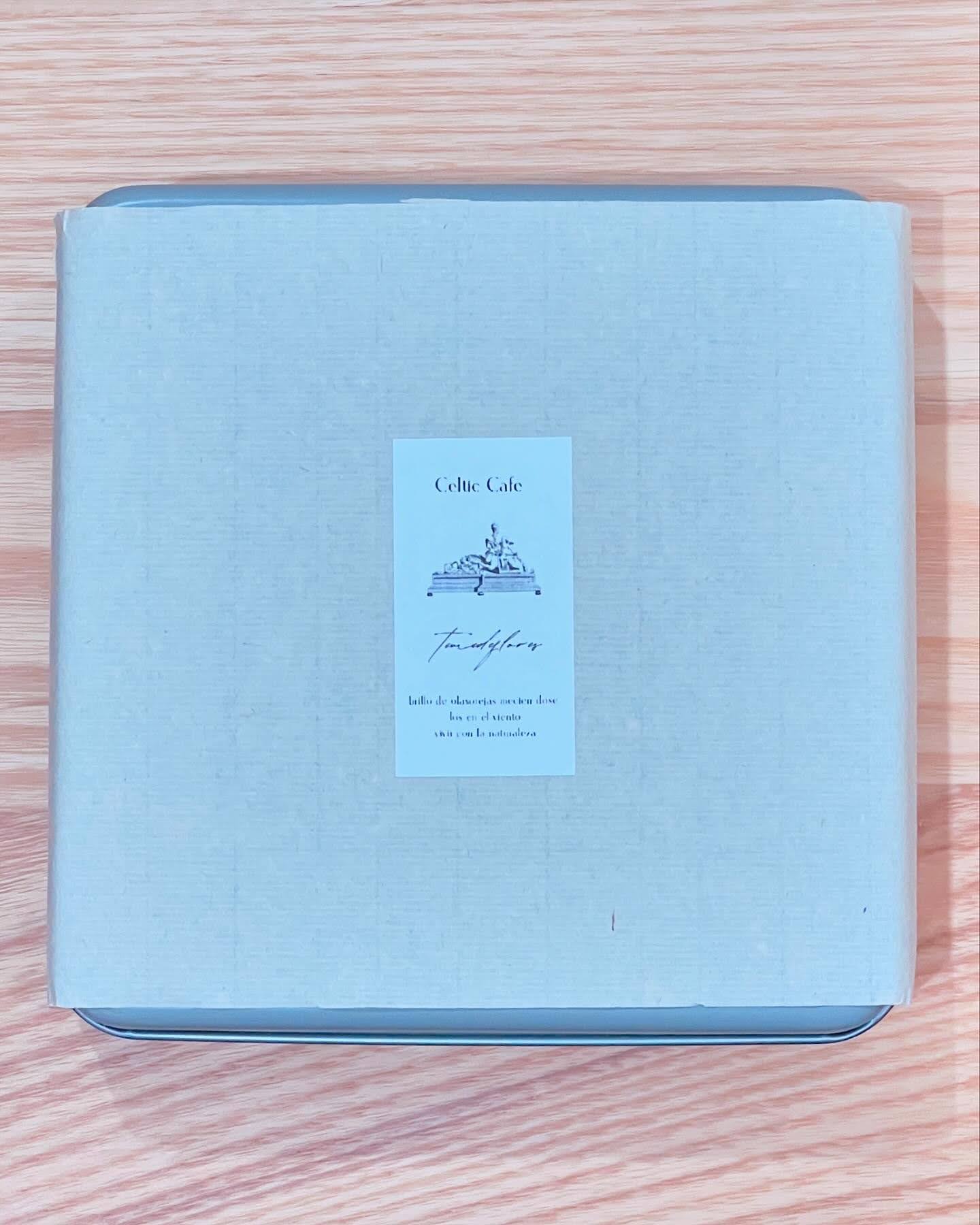“税の繰り延べ“の仕組みを正しく理解し、目先の税額に惑わされずに、会社の成長に繋がる経営判断を行うためのポイントを考えてみます。
”税の繰り延べ”を理解する
一般的に「節税」として知られている手法、例えば生命保険への加入や高額な備品の購入などは、「税の繰り延べ」であることがほとんどです。
これは、ある年度の経費を増やしてその年の利益(と納税額)を減らす代わりに、将来の年度で利益が増える(結果的に納税する)という、いわば納税タイミングを調整する方法です。
納税タイミングを遅らせるだけなら意味がないように思えるかもしれませんが、法人税率は会社の所得によって変動するため、うまく活用すれば納税額を抑えることが可能です。
日本の法人税率は所得が800万円を超えると税率が上がる仕組みになっています。
税率が高いタイミングで経費を計上し、税率が低いタイミングで利益を計上できれば、結果的に節税に繋がります。
しかし、その逆を行えば、かえって納税額が増えてしまう可能性もあるため注意が必要です。
税の繰り延べ策を過度に行い、所得を800万円より大幅に低くしてしまうと、将来利益が計上された際に高い税率が適用され、かえって損をしてしまう可能性もあります。
最も効率的に法人税を抑えるには、会社の所得を800万円(税引前利益で約848万円)に近づけることを一つの目安として利益をコントロールしていくのが賢明です。
また、大きな経費である退職金の計画などを慎重に絡めたりしながら考えていくことが現実的です。
よくある「節税策」のメリット・デメリット
ここでは、多くの企業で検討される代表的な”税の繰り延べ”手法の仕組みと注意点について。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)
取引先の倒産に備えるための制度ですが、支払った掛金の全額が経費になるため、節税や積立の目的で利用されることも多いです。
- メリット
- 支払った掛金の全額が経費になる。
- 解約時には、加入期間に応じて掛金が返金される(40ヶ月以上で100%)。
- 決算直前に年払い(最大240万円)することで、その期の利益を大きく圧縮できる。
- デメリット・注意点
- 節税になるのは、掛金を支払った年度の税率よりも、解約して返戻金を受け取る年度の税率が低い場合のみ。
- 業績が良い時に加入し、業績が悪化した時に解約返戻金を受け取る、といった戦略的な活用が求められる。
中古車の購入
”4年落ちの高級車は節税になる”という話は、中古車の耐用年数の仕組みを利用したものです。
- メリット
- 3年10ヶ月以上経過した中古車は、耐用年数が短くなるため、購入費用を短期間(最短1年)で減価償却費として経費にできる。
- 購入初年度に大きな経費を計上できるため、その期の利益を大きく圧縮できる。
- デメリット・注意点
- あくまで経費計上を前倒しにする方法であって、トータルで経費にできる金額は新車と変わらない。
- 利益がそれほど多くない年に購入すると、所得を下げすぎてしまい、融資申請などに問題が生じる可能性がある。
生命保険
かつては節税の代表格でしたが、税制改正により、以前ほどの節税効果は期待できなくなっています。
- メリット
- 保険料の一部を経費にできる。
- 万が一の際の保障を確保しながら、税の繰り延べができる。
- デメリット・注意点
- 解約時に受け取る返戻金は利益(益金)として計上されるため、その年度の法人税が増加する。
- 税負担を軽減できても、支払った保険料というキャッシュアウトが伴うため、会社の資金繰りを圧迫しないか慎重な判断が必要。
「税の繰り延べ」と上手に付き合い、会社の成長に繋げる
経営セーフティ共済や生命保険の解約返戻金が入るタイミングで、役員退職金を支払って利益を相殺する、といった手法は「出口戦略」と呼ばれます。
確かにその年度の法人税はゼロになるかもしれませんが、注意が必要です。
赤字(欠損金)が出た場合、その赤字は翌年以降の黒字と相殺して法人税を安くすることができます。
しかし、解約返戻金と退職金をぶつけて利益をゼロにしてしまうと、この繰越欠損金のメリットが享受できなくなり、翌年度の税負担が重くなる可能性があります。
つまり、単に税負担を翌年に先送りしているだけ、というケースも少なくありません。
世の中で言われる「節税策」の多くは、納税のタイミングをコントロールする「税の繰り延べ」であり、以下の特徴を踏まえておくことがポイントになります。
- 税の繰り延べは、将来の税率が現在の税率より低くなる場合に有効。
- したがって、「法人税ゼロ」ではなく「所得800万円」を目安に利益をコントロールする。
- 倒産防止共済・中古車・生命保険は選択肢の一つ。自社の事業計画やキャッシュフローに合わせて慎重に判断する。
目先の納税額に一喜憂憂するのではなく、税の繰り延べの仕組みを正しく理解し、中長期的な視点で自社の利益計画や資金繰りと照らし合わせながら戦略的に活用していくことが、会社の持続的な成長に繋がるといえます。