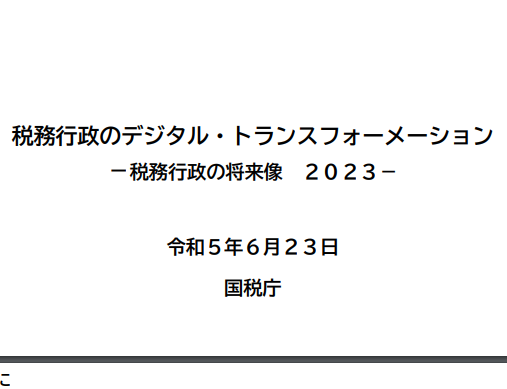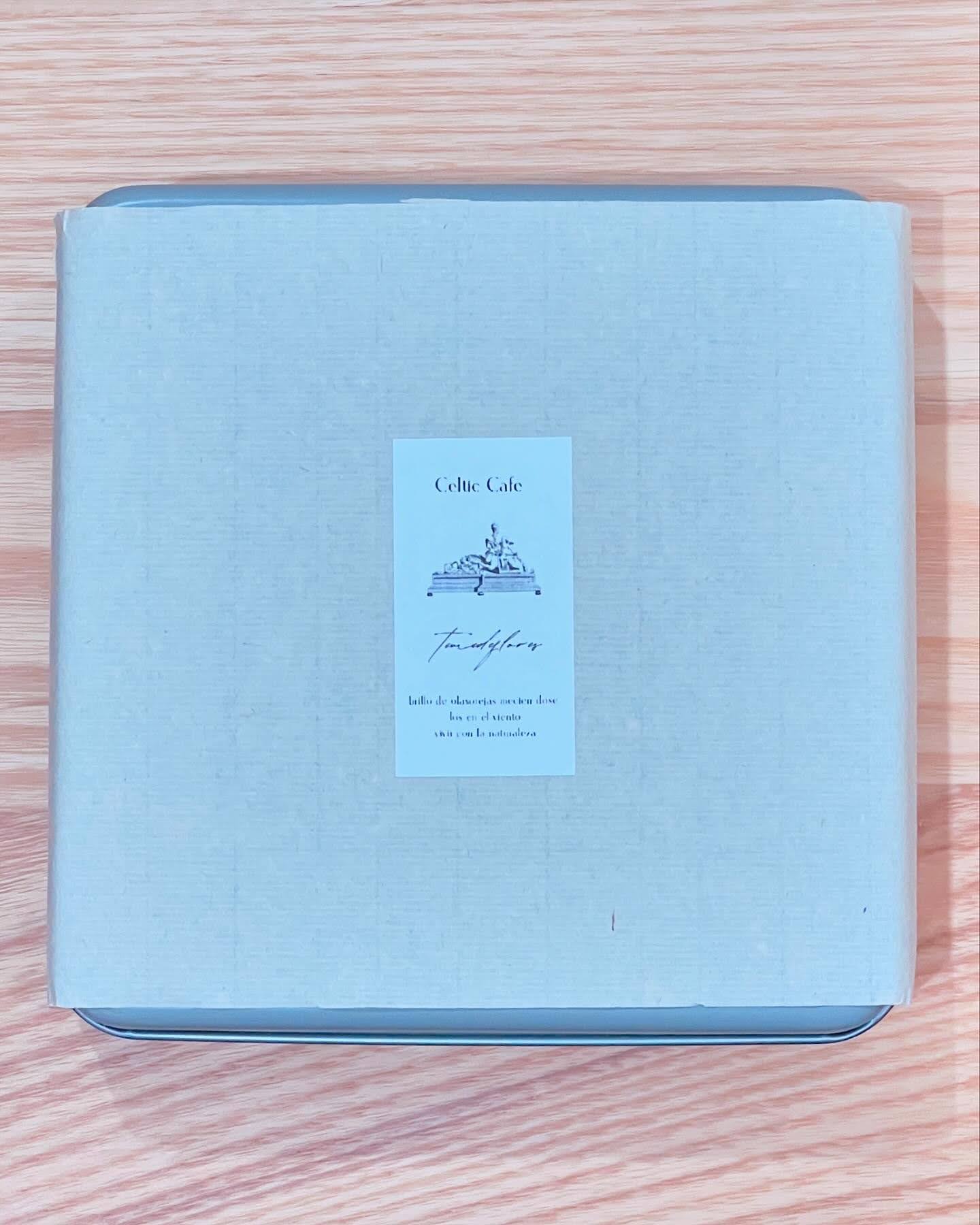多くの経営者が悩む役員報酬の設定。法人税以上に社会保険料の負担が手取り額に大きく影響しています。役員報酬だけでなく、株主である社長が受け取れる「配当」を組み合わせるとどうなるかという選択肢について考えてみます。
見落としがちな”社会保険料”の壁
多くの経営者が役員報酬を考える際、所得税や法人税といった「税金」に意識が向きがちです。
昨今それ以上に手取り額にインパクトを与えているのが「社会保険料」の存在です。
特に年収1,500万円以下の場合、所得税と住民税を合わせた額よりも社会保険料の負担の方が大きくなることがほとんどです。
会社の利益が800万円以下のケースで見てみると、法人税率は約21~23%ですが、社会保険料率は会社負担分と本人負担分を合わせると約30%にも達します。
役員報酬を増やして会社の利益を圧縮し、法人税を下げたとしても、それ以上に社会保険料の負担が増えてしまい、結果として会社と社長個人トータルで見ると、手元資金が減ってしまうという事態が起こり得ます。
会社と社長個人トータルでの手取りを最適化するには、税金だけではなく、この社会保険料と合わせたトータルの負担額で考える必要があるということになります。
「配当」という選択肢
役員報酬とは別の収入としてのもう一つの選択肢として、「配当」に着目してみます。
社長が100%株主である会社なら、その利益は社長自身が受け取ることができます。
役員報酬と配当の違い
| 項目 | 役員報酬 | 配当 |
|---|---|---|
| 社会保険料 | かかる | かからない |
| 会社の経費 | 経費(損金)になる(法人税が下がる) | 経費(損金)にならない |
| 支払いの原資 | 税引前の利益 | 法人税を支払った後の利益 |
役員報酬を少し減らし、その分を社会保険料のかからない配当で受け取ることにより、社長個人の手取り額を増やせる可能性もあるということになります。
配当のデメリットと注意点
配当は良い面ばかりではなく、以下の点には注意が必要です。
- 会社の経費(損金)にはならない
役員報酬は会社の経費(損金)として計上できますが、配当は税引後利益の分配であるため経費(損金)にはなりません。そのため、配当を支払っても法人税が減ることはありません。 - 利益の蓄積が必要
配当は、法人税などを支払った後の利益(税引後利益)や、過去の利益の蓄積(内部留保)から支払われます。そのため、創業したばかりで利益の蓄積がない会社では、配当を出すことは現実的ではありません。 - 他の株主への配慮
社長以外にも株主がいる場合、原則としてその株主にも配当を支払う必要があります。そのため、この考え方は社長が株式の100%(または大部分)を所有している会社で特に有効です。
最適なバランスを見つけるための着眼点
では、役員報酬と配当のバランスはどのように考えればよいのか。
社会保険料には上限額が設定されており、役員報酬がある一定の金額を超えると、それ以上は社会保険料が増えなくなり、収入を増やしたときの手取りの増加率が大きくなるという現象が起こります。
一方で、配当にかかる所得税や住民税は、役員報酬と合算した所得に対して決まるため、役員報酬が高い人が配当を受け取ると、高い税率が適用されてしまいます。
つまり、「社会保険料」と「税金」の両方の負担とが最も軽くなる最適バランスとなるポイントを見つけることが、手取りを最適化する上での鍵になってきます。
会社の利益水準ごとに、どのようなバランスが考えられるのか大まかな目安は以下です。
会社の利益水準別 最適バランスの考え方
| 会社の”実質利益”の水準(会社の利益+役員報酬) | 役員報酬と配当の最適なバランスの目安 |
|---|---|
| ~ 約1,000万円 | 役員報酬を低め(例:年間111万円~400万円程度)に設定し、社会保険料の負担を最小限に抑えます。 生活に必要な資金は、残った利益から「配当」として受け取ります。 |
| 約1,000万円 ~ 約2,000万円 | 会社の税引前利益が約848万円になるように役員報酬を考えます。 法人税率が低い範囲で会社に利益を残しつつ、残りを「配当」として受け取ることで、トータルの手取りが多くなる傾向にあります。 |
| 約2,000万円~ | 理論上はすべて役員報酬で受け取る方が有利になるケースが増えます。 ただし、会社の成長のため、あえて税引前利益を848万円程度残して「内部留保」とし、残りを役員報酬とする考え方が推奨されています。 |
ここまで社長個人の手取りを最大化する視点でお話ししてきましたが、必ずしもそれが唯一の正解とも限りません。
会社が生み出した利益のすべてを社長個人に移すのではなく、一部を「内部留保」として会社内に残しておくことも、経営において非常に重要です。
潤沢な内部留保は、以下のようなメリットをもたらします。
- 未来への投資: 設備投資など、事業を拡大するための原動力になります。
- 財務基盤の強化: 金融機関からの信用が高まり、融資を受けやすくなります。
- リスクへの備え: 予期せぬ事態が起きた際に、会社を守る体力となります。
社長個人の手取りを最適化しつつ、会社の成長のために内部留保も確保する。両者のバランスを考え、自社にとっての最適な「役員報酬」と「配当」の組み合わせを見つけることが、会社を長期的に発展させるための賢明な選択といえます。