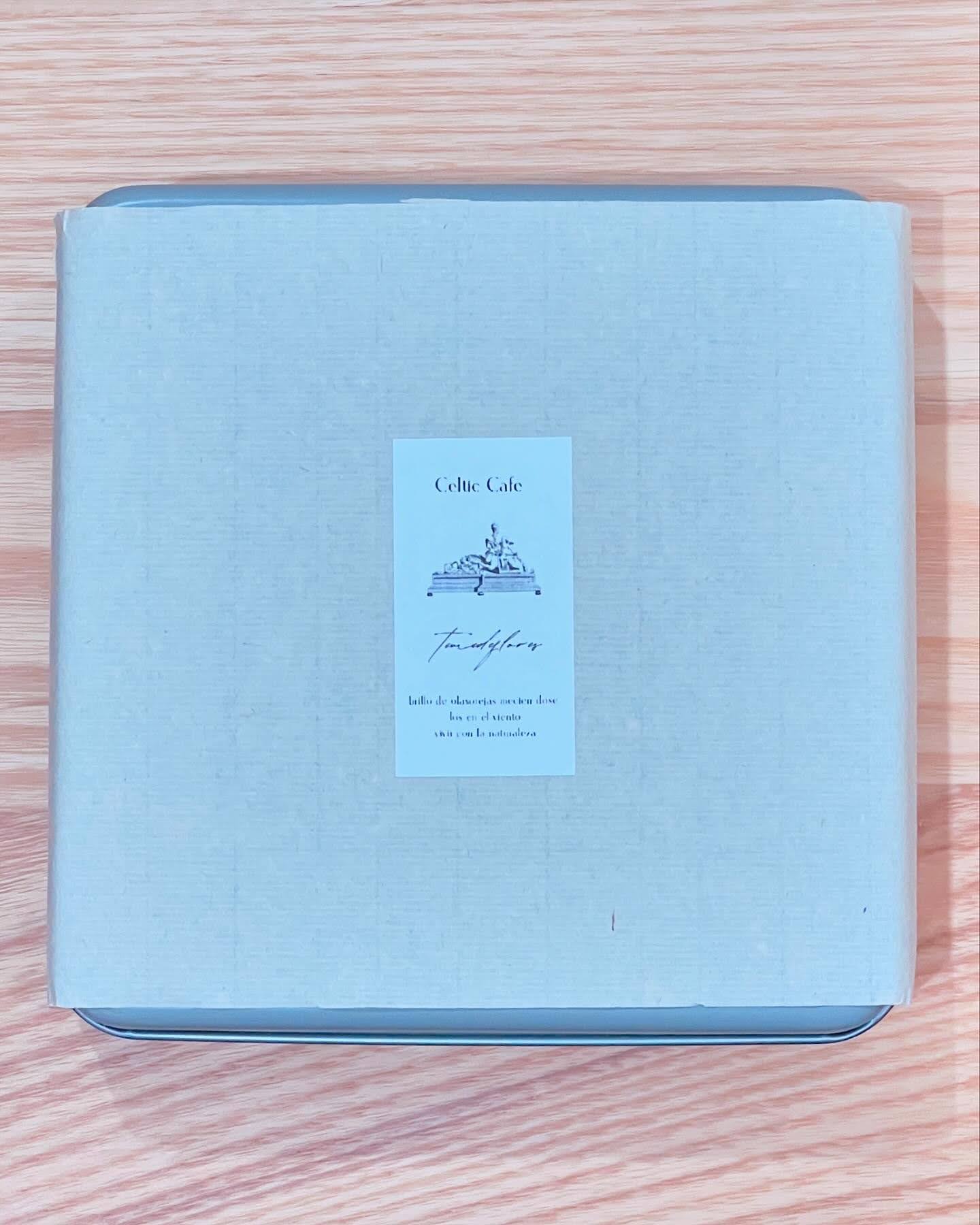福利厚生費に着目し、会社の成長と個人の資産形成を両立するための具体的な活用術について考えます。
「給与」と「経費」の違い
会社が支払う「給与」と「経費」では、キャッシュアウトの総額が異なってきます。
例えば、会社が1万円のコストをかける場合を考えます。
- 「給与」で支払う場合
会社は社会保険料の会社負担分(約15.4%)を上乗せする必要があるため、キャッシュアウトは約11,541円となります。 - 「経費(福利厚生費など)」で支払う場合
会社が支払うキャッシュは1万円です。消費税の課税対象であれば、さらにその分の控除が見込めます。
福利厚生の活用6選
具体的に、福利厚生をどのように活用すれば会社の財務体質強化に繋がるのか。
旅費日当
出張は多くの企業で発生する経費ですが、旅費規程を整備し、旅費日当を支給することにメリットがあります。
給与のように社会保険料という付随コストが発生しないため、会社は出張にかかる総費用を正確に予測し、予算管理の精度を高めることができます。
社宅制度
会社が社宅を提供することで、同等の価値を給与に上乗せして支払う場合に比べて、社会保険料の負担増を回避できます。
従業員から一定額以上の家賃を受け取っていれば、実際の相場家賃と会社が支払う賃料との差額は給与として課税されません。
食事補助(ランチ・残業食事代)
残業時の食事は福利厚生費として補助することが可能です。
また、昼食の場合、月額3,500円(税抜)までの補助など一定の要件を満たすことで、福利厚生費として補助することが可能です。
福利厚生サービス、研修費
福利厚生サービスの活用や、研修も、検討の余地があります。
- 福利厚生サービス
福利厚生サービスを利用すれば、煩雑な精算業務などが不要となり、管理部門の業務コストを削減できます。また、月々の会費として費用が固定化されるため、予算計画が立てやすくなるメリットもあります。 - 研修費・旅費交通費の活用
事業成長に不可欠な人材育成のための研修や視察にかかる費用は、会社の「研修費」や「旅費交通費」として計上可能です。
会議費・交際費
事業に必要な会食費用であれば、社長個人のポケットマネーで支払うのではなく、会社の経費として計上可能です。
退職金制度
「中退共(中小企業退職金共済)」、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」、そして近年注目されている「はぐくみ企業年金」といった外部積立制度を活用可能です。
「中退共」は従業員向けですが、「はぐくみ企業年金」は役員も加入対象にできるなど、それぞれに特徴があるため、自社の状況に合わせて最適な制度を選択することが重要です。