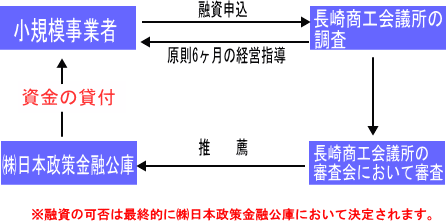銀行では、融資申請する企業の決算書をどのように捉えているか。
諸留誕著「顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック」(日本法令)を参考にして。
損益計算書の表示を工夫する
事実をどのように損益計算書へ落とし込むか・表示するかによって、銀行への印象も代わりますし、表示を工夫することでよい変化が生じるのであれば、ぜひ検討したいところです。
実態に伴わない表示をしないようにする
損益計算書の表示について工夫する余地があるのですが、かといって、実態と乖離した表示をすべきではないと思われます。
例えば、以下のような事項について留意が必要と思われます。
特別利益とすべきものを営業外収益に表示しないようにする
経常利益を大きく見せるために、本来は特別利益とすべきものを営業外収益に表示すべきではないと考えられます。
営業外収益に表示するには、そのための理由付けは必要と考えられます(少額であるため、毎期継続的であるため、など)。
例えば、有価証券売却益、固定資産売却益などです。
実態面から特別利益としたからといって必ずしも損するものでもなく、”財務改善のために遊休資産の売却処分を行った”などのアピールをすればよいということになります。
訴訟費用の表示区分について
訴訟費用の表示区分については、ケースバイケースであると考えられます。
特別損失として計上するケースもありますが、逆にそのことでネガティブな印象を与えることは拭えないものです。
そのため、決着を見るまでは、その弁護士費用等を支払報酬・支払手数料として計上し、決着してから結果を銀行に伝えるというケースも考えられます。
当期の税金を当期に計上する
税金を支払ったときに費用計上するという選択肢もありますが、その場合、当期の税金が翌期に表示されることになってしまい、当期利益と当期税金といった対応関係が取れなくなってしまいます。
銀行側も、税引前当期利益とその税額とが対応関係にあるかを見ているものです。
そのため、税務上の多額の加減算がある場合には、あらかじめ銀行に伝えておいたほうがよいと思われます。