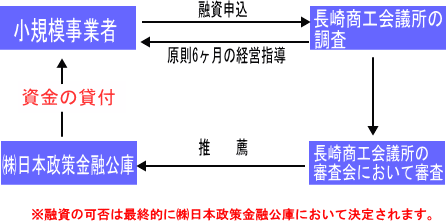融資申請の際には、借入希望額を記載する欄があり、どのように決めてよいのか迷いがちです。
諸留誕著「顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック」(日本法令)を参考にして。
”いくら借りられるのか”とは聞けない(聞いてはいけない)
融資を申し込もうとする際、「借入希望額」を記載したり、伝えたりすることになります。
ここで、銀行に対して”いくら借りられるのか”と聞くと、”計画性がないのではないか”という印象を与えてしまうことになってしまいますし、基本的に聞いてはいけないものではあります。
自社の事業計画において、「いくら必要なのか」が明確になっているべきものだからです。
”いくら借りられるのか”を自分で考えるには(全般)
”いくら借りられるのか”を自社でどのように推し量ればよいのか。
いくつか尺度があり、参考にしたいところです。
借入金月商倍率
「平均月商の6倍以内」が目安となります。
総資産借入金比率
「借入金残高/総資産が70%以内」が目安となります。
「債務償還年数」をベースに考えるパターン
- 「債務償還年数」を計算する(借入残高/(税引後利益+減価償却費))
- 「10倍未満」が望ましい=10倍まで借りることができる
- 現状の借入金額残債は除くことになる
- (税引後利益+減価償却費)×10倍-現状の借入金額残債
上記の枠に、運転資金を除外して考えるパターン
「(税引後利益+減価償却費)×10倍-現状の借入金額残債-運転資金」
というように、運転資金を除外する考え方もあります。
これは、運転資金とは、資金繰りの安定化のために必要なものであって、返済に利益は必要ないという考え方によるものです。
運転資金とは、「売掛債権+棚卸資産-仕入債務」で表すことができます。
上記の枠に、現金預金を除外して考えるパターン
「(税引後利益+減価償却費)×10倍-現状の借入金額残債-現金預金-運転資金」
というように、現状の借入金額残債から、現金預金を除外することで、”実質借入金”のみを除外するという考え方です。
創業融資の場合の考え方
創業融資の場合、実績がないため、「自己資金の3倍」が目安とされます。