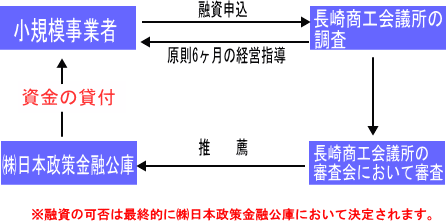銀行は融資先の格付けをどのように行っているのか。
諸留誕著「顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック」(日本法令)を参考にして。
融資先格付を決める流れ
銀行は融資先の格付けを行っていますが、そもそも何のためにそれを行っているのかというと、金融庁との関係上、自己査定をしなければならず、その自己査定のベースとなるものが格付・債務者区分であるというものです。
では、その融資先への格付けをどのように決めているのか。
以下のような段階でもって決めていると考えられています。
- 第1段階:定量評価
- 第2段階:定性評価
- 第3段階:実態評価
第1段階:定量評価
決算書を点数化し、定量評価することが第一段階となり、以下の13指標で決められているといわれています。
- 売上高
- 自己資本額
- 自己資本比率(純資産/総資産)
- 収益フロー(何期連続で黒字か)
- キャッシュフロー額(営業利益+減価償却費)
- 流動比率(流動資産/流動負債)
- インタレスト・カバレッジ・レシオ((営業利益+受取利息配当金)/支払利息割引料)
- 債務償還年数(借入金/(営業利益+減価償却費))
- ギアリング比率(借入金/純資産)
- 売上高経常利益率(経常利益/売上高)
- 総資本経常利益率(経常利益/総資本)
- 経常利益増加率((当期経常利益-前期経常利益)/前期経常利益)
- 固定長期適合率(固定資産/(固定負債+純資産))
諸留誕著「顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック」(日本法令)においては、以下の3要素を良くすることでおのずと上記の13指標は改善してくるとしています。
- 簡易キャッシュフロー(税引後利益+減価償却費)
- 債務償還年数((借入金残高/簡易キャッシュフロー)<10)
- 債務超過の有無
もっと突き詰めると、”利益を増やすこと”に集約されることになります。
第2段階:定性評価
第2段階として、点数化できない要素での定性評価であり、以下の11項目で決められているといわれいます。
- 市場そのものの動向
- 市場規模
- 競合状態
- 景気感応度(景気の影響をどこまで受けるか)
- 業歴
- 経営者の資質・経営方針
- 株主の安定性
- 従業員のモラル
- 営業基盤の強弱
- 競争力
- シェア
定性評価のアピールとして有効なものは、やはり「経営計画書」であり、これらを作成・文書化・提示することにより、よりストレートにもれなく銀行に伝えることが可能になると考えられます。
第3段階:実態評価
最終的に、銀行側で実態評価という観点で修正を行っていきます。
銀行側のロジックはまちまちで、会社側の努力としては、ごまかしなく正確に誠実に伝えることではありますが、それら以外では、”社長の個人資産の充実度を高める”ということが重要であると考えられます。