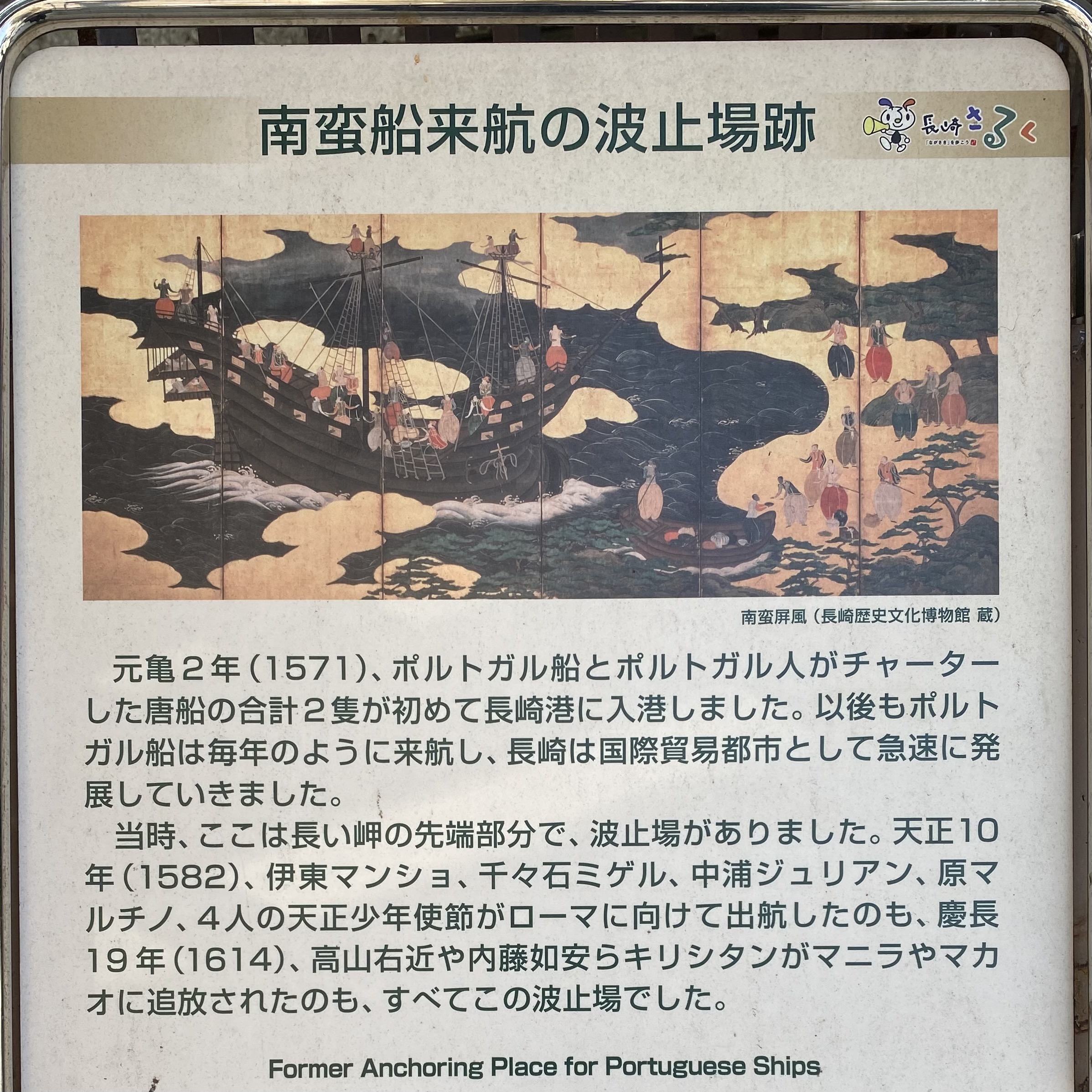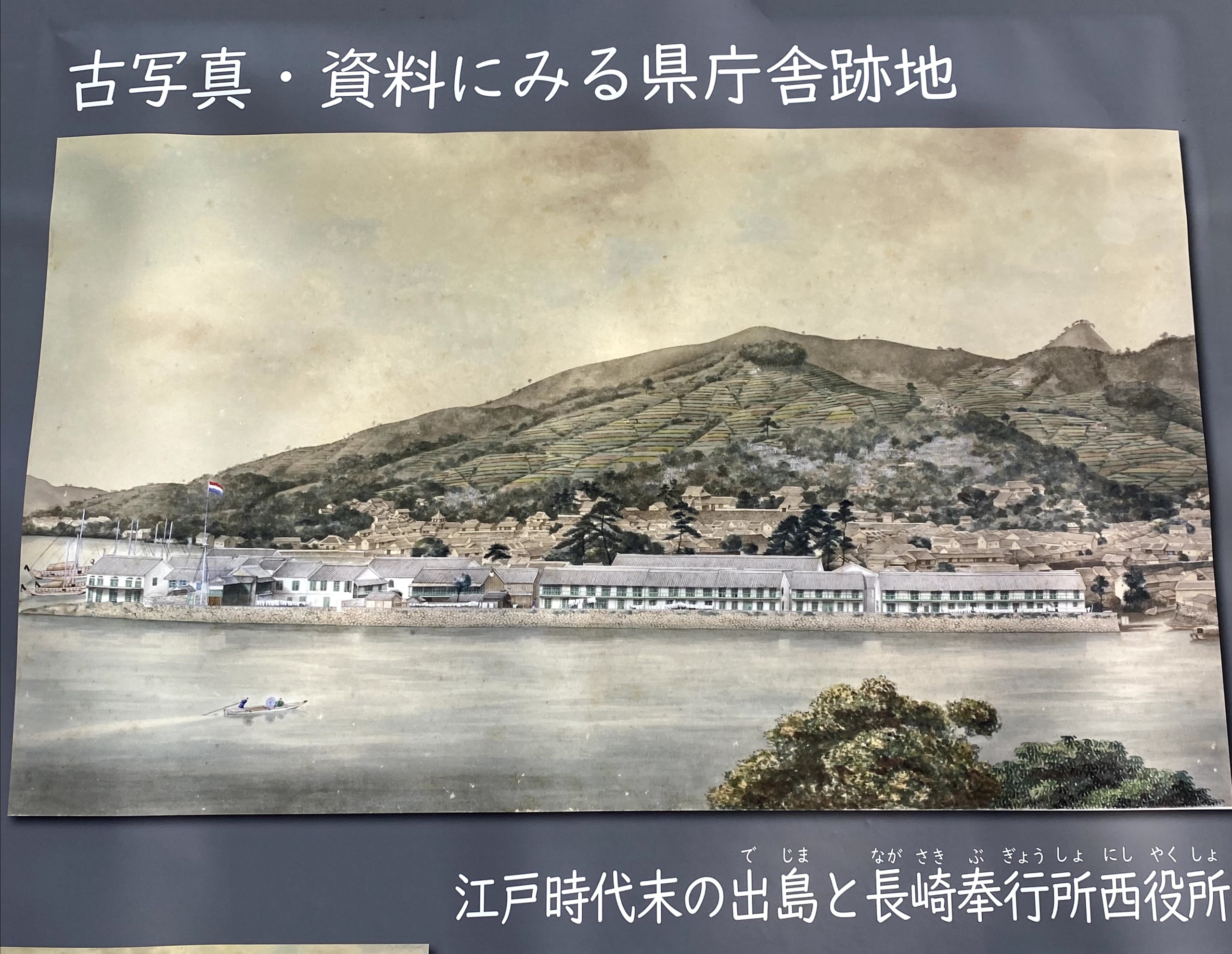物事の全体像を掴もうと思うと、2つの目で見ていく必要がありそうです。
河合隼雄「こころの処方箋」(新潮社)を読んで学んだこと。
1つの目で見ると見落とすことがある
物事に対し、表面でしか見ないと、見落とすことがあります。
例えば、口で「やります」と言っていた人が、実はやっていなかったり。
口での説明だけを聞いてしまうと、それしか見えずに判断してしまいそうですが、
「やります」と話したときの非言語の部分、すなわち、話しているときの目の動き、言い淀んだり、落ち着きがなかったりする部分まで目を向けることができていれば、あるいは、「やります」と言いながらもできない何らかにまで気づくことができていたかもしれません。
立体的に見ていく
物事の全体像を把握しようと思うと、目に見える部分のみならず、正面からは見えないその物事の「奥行き」にまで目を向ける必要があります。
立体像として把握する癖をつける、という感覚です。
ここで大事なのは、それぞれの目で見ているものが1つの対象に繋がっている見方をすることなのだろうと思います。
先ほどの例でいえば、「やります」という言葉と、目の動き・言い淀み・落ち着きのなさがそれぞれバラバラに見えていたとしても意味がなさそうです。
それぞれで見たものを統合し、目の前のその人の葛藤や気持ちを把握しようとしなければ、立体的に見えてこないということですね。
どのような”2つの目”があるか
「言語」と「非言語」は1つの例で、「主観」と「客観」、「楽観」と「悲観」など色々な組合せが考えられます。
そのときそのときに応じた”2つの目”がありそうです。