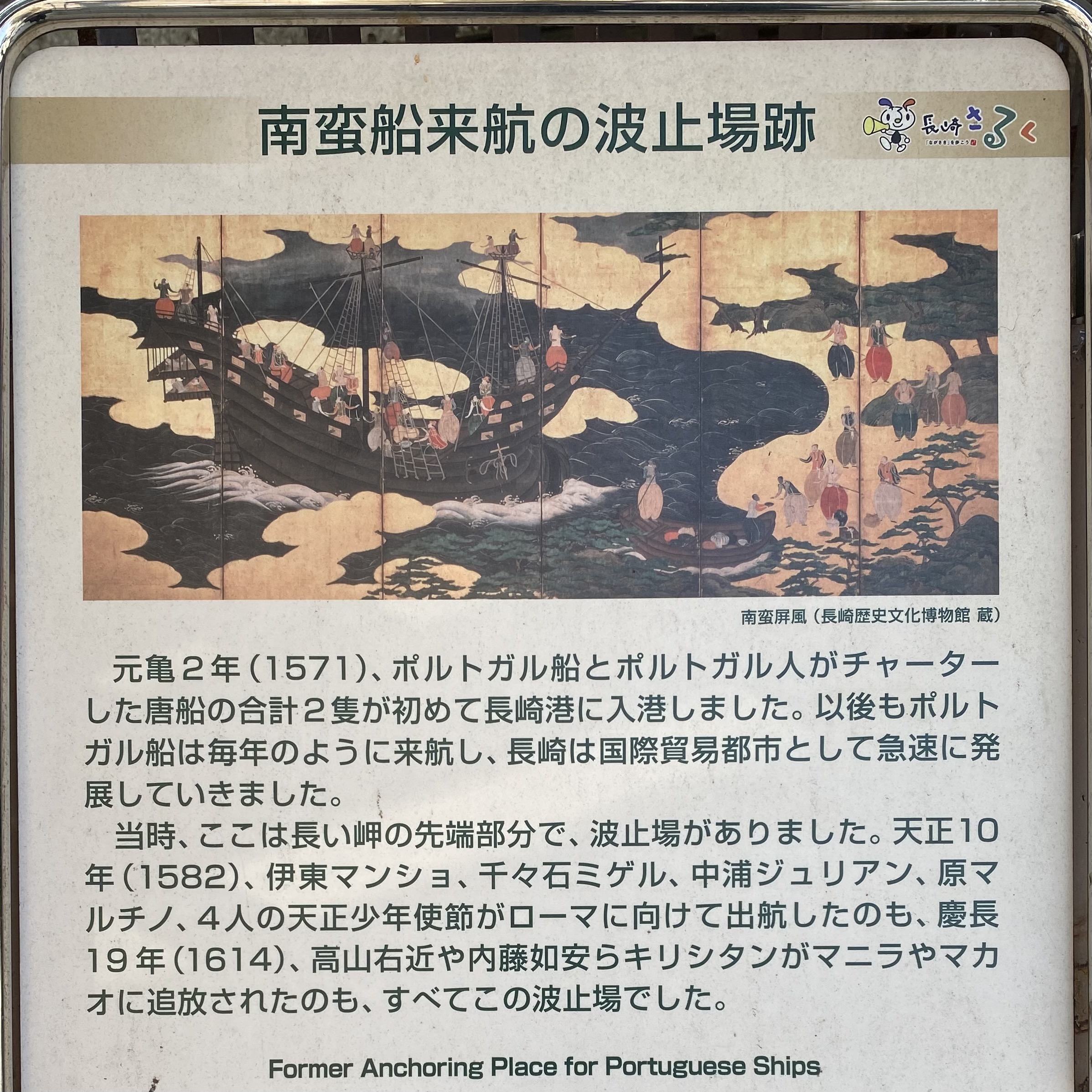会議では、議題を決めて話し合って意思決定をし、その後はその決定に即して行動していけるということが理想的です。
一方、特に幕末薩摩藩の有名な郷中教育のなかの会議の手法に、「詮議」というものもあります。
河合隼雄「こころの処方箋」(新潮社)を読んで学んだこと。
欧米民主主義での「会議」
河合隼雄「こころの処方箋」(新潮社)を読んでいて、興味深い話題がありました。
欧米の民主主義は個人主義の確立を前提に成立っている。アメリカの高校は非民主的でも権力主義でもなく、校長の提案に対して、すべての教員がそれに意義をとなえる権利をもっている、という意味で民主的なのだ。もし異議のある人は、校長案に対して対案を出し、それは全員で討論され、全員の意志でどちらかに決定されるだろう。「争点」が明確にされ、それについて論じられる。
これに比して、日本の場合は、多くの発言者は、「こんな場合はどうだろう」とか「こんなことも考えているか」などと、細部にわたって疑問を提出するが、「争点」は不明確で、「対案」をもっていないことが多い。
河合隼雄「こころの処方箋」(新潮社)より
確かに、日本の会議のイメージでいうと、全体のバランスが大事にされ、ゴツゴツと意見がぶつかるような場は想像しづらい気がします。
一方で、「こんな場合はどうだろう」「こんなことも考えているか」等、細部にわたって内容を詰めていくような話し合いは、割とよくある形のような印象も受けました。
反実仮想(ケーススタディ)
以前、歴史学者の磯田道史先生が書籍やインタビューで、幕末薩摩藩の教育システムである郷中教育のなかの「詮議」というディベートが「反実仮想」(ケーススタディ)のトレーニングになっており、そのトレーニングが幕末の目まぐるしい環境のなかで、薩摩藩が勝ち残っていく原動力になった、という話をされていました。
さらには、この「詮議」教育は、薩摩藩だけで行われていたわけではなく、戦国時代くらいまでは日本各地で行われていたものであるようです。
もしかしたら、日本の会議における「こんな場合はどうだろう」「こんなことも考えているか」といった会議風景は、これらが起源になっているのかもしれません。
このような反実仮想(ケーススタディ)を主体とした会議方式は、その良さも多分に感じます。
上記の会議方式によって日本の特徴である”細かなところまで行き届いた商品・サービス”を作り上げられたと言われたとしても、なんだか納得する感じもします。
会議で何を目的にするか
「詮議」(反実仮想(ケーススタディ))にばかり終始してしまい、「争点」が不明確となり、発言者が「対案」を持っているというわけでもない、ということも言えるのかもしれません。
「詮議」(反実仮想(ケーススタディ))にも良さがあり、反面、良くなさもある、ということでしょうか。
そういう意味では、やはりまずは会議の目的を明確にし、それに沿った対話方式を目指す、ということに尽きるのかもしれません。

薩摩藩士ら(小松帯刀・五代友厚)によって計画された修船場

薩摩藩士ら(小松帯刀・五代友厚)によって計画された修船場