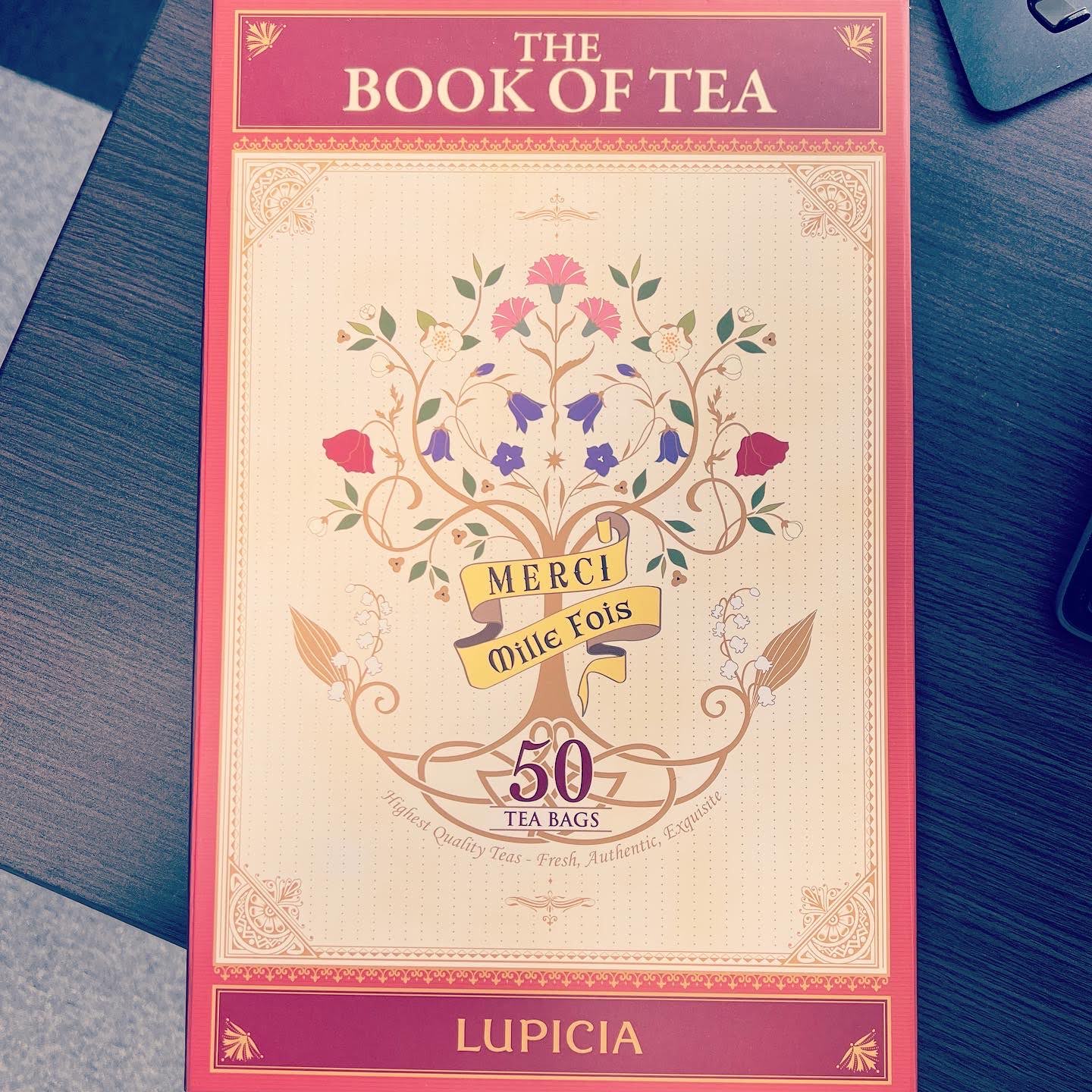「様子を察して考える」は、スタンスもセンスも出やすいように感じます。
齊藤三希子「パーパス・ブランディング」(宣伝会議)を参考として。
様子を察して考える
「相手の様子を察して、その人のためにできることを考える」
これができるかできないか。
できるとして、何を察し、どのように表現するか。
これには、スタンスもセンスも出やすいように思います。
”察する”という言葉どおり、対象は、”まだはっきりとは表面化していないかもしれないこと”です。
それを敏感に感じ取って、すくい上げて、相手のためにできることがないかを探す。
共感レベルが高くないとできないことですし、人としての感性も必要とされます。
マニュアルに落とし込むものではない
再現性が低い、という側面もあるかもしれません。
”察するべき相手の何か”をパターン化して掴まえるということにはどうしても限界があります。
察するというスタンスを持つだけでもアンテナを張るようになりますし、マニュアル化されたとしてある程度のパターンは掴めるかもしれません。
そこからさらに高めるには、やはり個々人の経験やセンスにもよってくる気がします。
何をベースにアンテナを張っているか
事業においては、一期一会な部分があります。
同じ人であっても、同じ状況というものは何度も訪れるものでもありません。
その一期一会の状況には咄嗟の考えや対応が求められ、付け焼き刃の対応は難しい部分があります。
常にアンテナを張り、共感レベルを高め、”察する→考える→行動する”のサイクルをトレーニングすることでしか、高まっていかない分野な気がしています。
また、そのアンテナを、何をベースにしているかも大きいように思います。
自社の存在意義が明確であれば、そのベースとなる部分も明確となり、より気づきやすい面も出てくるように思います。