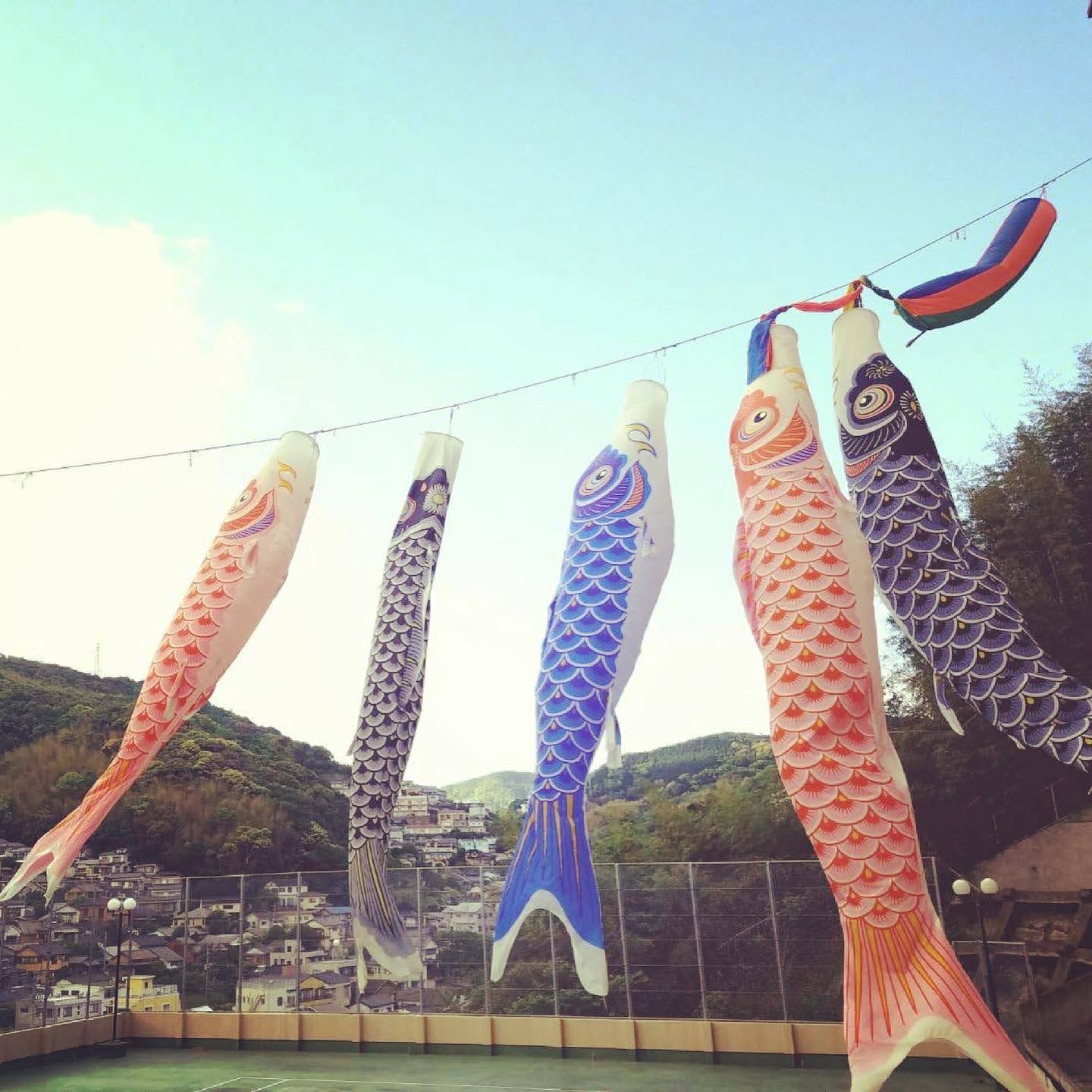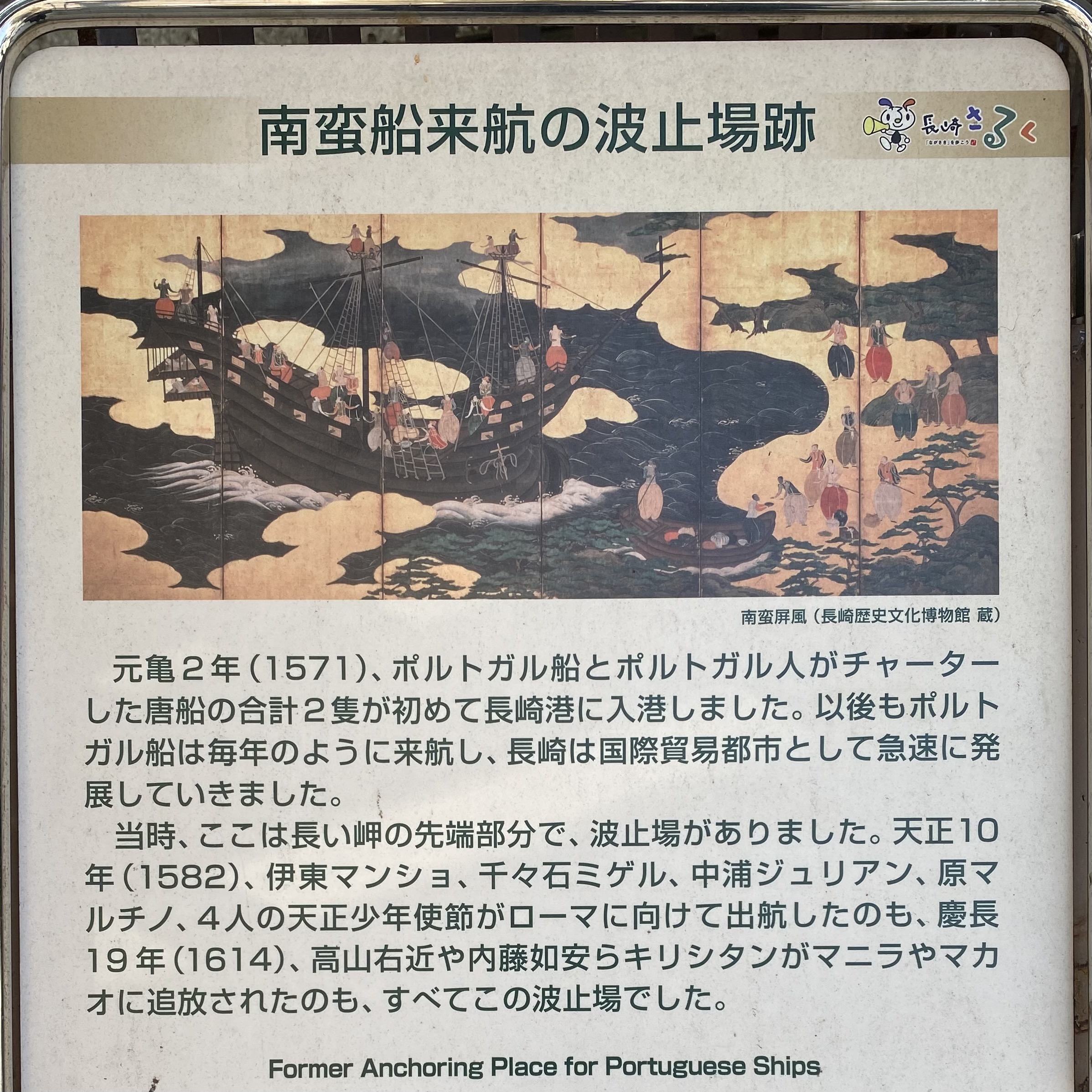暗闇でどこへ向かうべきか分からなくなってしまったとき、逆説的ながら、あえて手元の灯を消すと、目が闇に慣れてきたり、星の光の助けも借りることができたりで、行く手が分かるときがあります。
河合隼雄「こころの処方箋」(新潮社)を読んで学んだこと。
暗闇で不安になる
河合さんの「こころの処方箋」のなかで、河合さんが昔印象を受けた話として、以下のような話がありました。
何人かの人が漁船で海釣りに出かけ、夢中になっているうちに、みるみる夕闇が迫り暗くなってしまった。あわてて帰りかけたが潮の流れが変わったのか混乱してしまって、方角がわからなくなり、そのうち暗闇になってしまい、都合の悪いことに月も出ない。必死になって灯(たいまつだったか?)をかかげて方角を知ろうとするが見当がつかない。
河合隼雄「こころの処方箋」(新潮社)より
そのうち、一同のなかの知恵のある人が、灯を消せと言う、不思議に思いつつ気迫におされて消してしまうと、あたりは真の闇である。しかし、目がだんだんとなれてくると、まったくの闇と思っていたのに、遠くの方に浜の町の明りのために、そちらの方が、ぼうーっと明るく見えてきた。そこで帰るべき方角が見えてきた。そこで帰るべき方角がわかり無事に帰ってきた、というのである。
自分の行くべき道が見えなくなったとき、どうにかして灯りをかき集めて、行く道を照らしたいと思うのは自然なことです。
不安でもありますし、藁をもすがりたい気持ちから、なんとか手元の灯りを増やしたり、頼ったりしてしまいがちです。
手元の灯をあえて消す
その手元の灯をあえて消す、というのはとても示唆的です。
手元の灯をあえて消すことで、自分の目で暗闇をなんとか見ようとしているうちに、やが目が暗闇に慣れて、ふと見えるようになったり、あるいは、思わぬ星の光の助けもあったりで、手元の灯がない方がかえって見えるようになる、ということです。
自分の目で見ようとすることで見えてくることがある
”手元の灯”というものは、そもそも外部から与えられ、調達するような類のものです。
不安な気持ちから、なんとか灯を集めなければと思い、藁をもすがる思いで、あれこれと求めてしまいがちです。
しかし、あえてそのようなものを捨てて、目をこらして先行きを見ようとする勇気や試みは、ときとして必要なのだろうと思います。
何事にも不安はありますし、あれこれと外のことが気になったり、求めてしまったりしがちです。
ときには、あえてそのような視点をいったん捨て、「自分の目」で、自分の先行きを目をこらして見る勇気も必要ですね。




奥の山が、御船山です